苦労の末に完成した、リッチアロマティーシリーズが展示会デビューを飾った矢先
社員との感覚のズレが日を追うごとに増していき、最終的には大きな問題を呼ぶことになりました。
香りと紅茶では、売り場も違えば、取引先も違ってきます。
営業はもちろん一からのスタートとなります。
私の中では同じだと言い張ってみても現場では理解できずに消化不良を起こしていたということなのです。
社内では孤立し、四面楚歌の状態でした。それからの私にはさらなる試練が待ち受けていました。
そんなときに弊社にとっても忘れることのできない事件が起きてしまったのです。
認識の甘さが招いた、間違った選択
弊社は香り雑貨のメーカーですので、食品加工に関してはすべてを外注して委託生産をして貰っていました。
時代はちょうど有名食品会社の不正事件や賞味期限の改ざん問題で大変なざわつきの起こっていた時でした。
パッケージなどの副資材はすべてを委託先に供給して生産をしてもらっていたわけですが、紅茶のパッケージに貼る消費期限のシールを大量に貼り間違えたという知らせが、工場から弊社の担当者に入ります。
その時は弊社の担当者と委託先の工場長とが話し合った結果、ラベルをきれいに上から貼りなおすという、あってはならない選択をしてしまったのが事の発端でした。
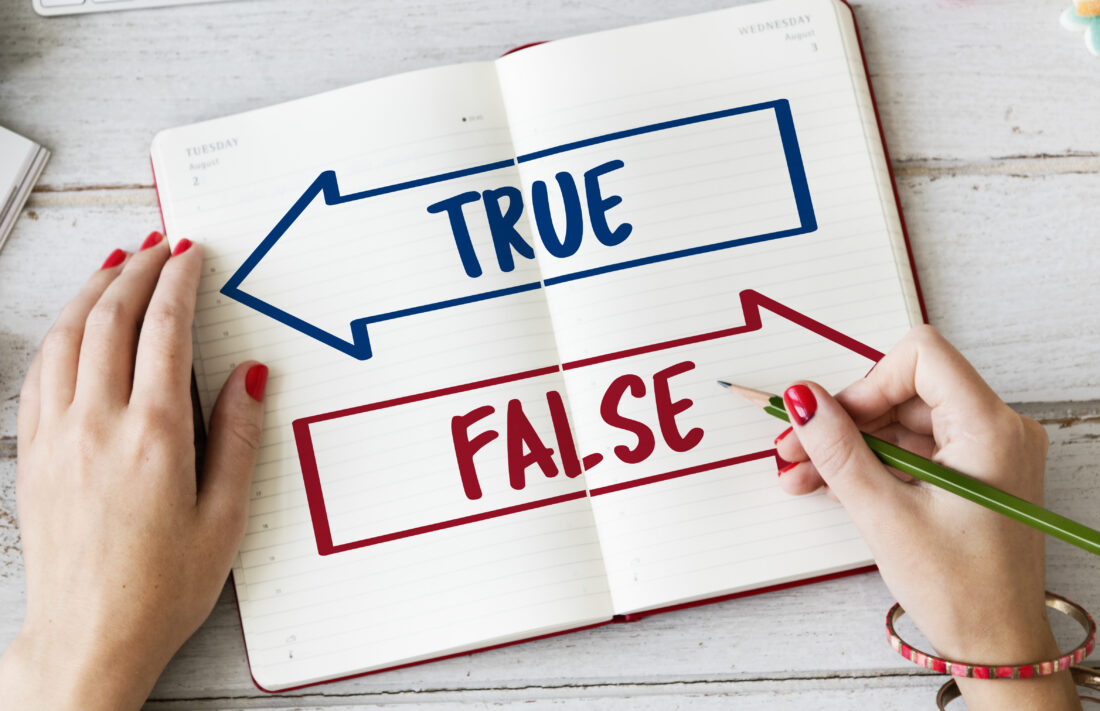
問題の発覚、そして消費者センターからの調査
事件は、都内の某有名百貨店の食品売り場で起こります。
お客様が購入されたパッケージの裏面シールを見ると、かすかにその下にもラベルが貼られていることに気づかれたようでした。
このようにして社会全体が消費期限の改ざん問題に非常に強い関心を持っていた状況下で事は重大な事件へと発展してしまったのです。
そのお客様は、消費者センターに電話を掛けます。消費者センターからは当然百貨店の売り場へと問い合わせと調査依頼がされました。
私が百貨店の食品売り場の部長様から電話を受けたのは早朝の6時頃でした。
「高木社長でしょうか?食品部の〇〇と申しますが、お客様からクレームがございまして、大変恐縮ではございますが急を要しておりますので本日私共の本部までご足労お願いいたします」
寝起きのぼやっとした頭のまま、何が起きたのかもおぼろげな状態で、私は新幹線に乗り都内の某所まで駆け付けました。
部長職の方でしたが食品部は売り上げもよく花形部署であることからかお名刺には役員のタイトルもついていました。
間違いが発端としても致命的なミス
ことの一部始終の説明を受けた私は、信じられない思いでしたが、工場での事情を初めて確認して事の重大さに身が震えました。
間違えて貼ったといっても、もとの日付の消費期限の方が貼りなおした消費期限よりも、もっと先の日付であったならば、即ち、消費期限を短くするように張っていたのならまだ許されるかもしれませんが、事もあろうことか消費期限を故意に伸ばしたとしか思われない先の日付のラベルが貼られていたのです。
致命的としか言いようもない現実がそこにありました。
「あぁ、会社ってこんなふうにして、いとも簡単につぶれてしまうんだな…」と。
もうすべてが終わったように感じました。

その部長の前で土下座をしようと椅子から腰をあげてその椅子の横に膝間づいた瞬間でした。
「髙木社長、それはやめていただけますか!どうぞもとにお直りください」
一部始終わたしの涙ながらの説明を聞いていたその部長は、「高木社長がその内容で嘘をつかれているとは私には思えません。
本当でしたら全品引き上げはおろか、すべての全国紙の新聞広告に謝罪文を載せていただいてご購入された方々へも謝罪をしなければいけないことなのですが…、失礼ですが、今のご時世ですとそれはイコール会社をつぶすことに繋がります」
「もうお分かりかと思いますが、大手の食品会社の数々の不正で世間の目もより厳しい状況です。
私にはあなたの会社を潰す権利は持ち合わせていません。ですので、私がうまくいくように社内で動きますので、今日はお引き取り頂いて結構です。」
「しかしながら、弊社とのお取引口座は抹消ということになります。それでご了承いただけますか?」
私の目からは もうすでに涙が溢れていました。
今、思い返しても体中に震えを覚えますが、その部長様には感謝してもしきれないぐらいの対応をしていただきました。
その日以降のことは恥ずかしながらよく覚えていません。
何をどのようにして処理して、誰に謝罪したのか、どなたに迷惑をおかけしてどなたに助けていただいたのか・・・。
情けないことですが、当時私はいっぱいいっぱいだったのでしょう。
そして、理由はそれぞれだったでしょうが、社員も一人二人と去ってゆきました。
結果的には独りで考えて一人で動いて、独りで招いてしまった失敗と言えると思っています。
経営者が目の前にあるチャンスを急いで掴みに行こうとするのは、つねに現状に危機感を持っているからなのですが、周りの社員たちは感覚的にはなにも分かりません。
それは極々当然のことなのですが、そこの間の感覚を少しでも埋める方法を模索せず努力を怠るとこのような悲惨な事態に巻き込まれてしまうという教訓だと、今では思っています。
